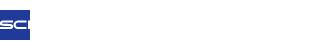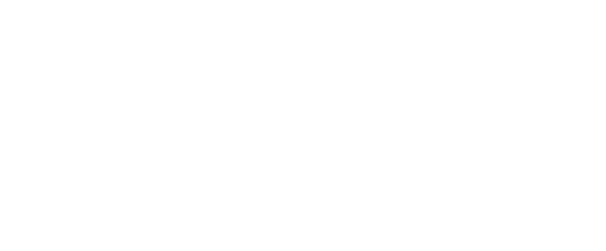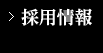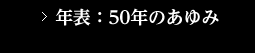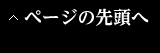株式会社三祐コンサルタンツは今年で創立50年を迎えました。会社が産声をあげたのは、ようやく戦後の高度経済成長が始まった頃。その2年後、昭和39年から私たちは海外での水資源開発プロジェクトに携わってきました。
見渡すかぎりの砂漠。
無力な太陽と渇ききった風。
地図に記されることもない小さな村々。
虚空に向かって吠える犬。
この世の理不尽にさらされる子供たちの、胸が張り裂けるようなあどけない笑顔。
鳥の目に宿る哀しみも見てきました。
千年を一日のごとく過ごす大きな地球の営みの前に、私たちの力はあまりにも弱い。
まるで恐竜に素手で立ち向かう少年のように…。
一本の水路を引くだけで枯れ果てた地は見る間に緑を帯びてきます。広い砂漠なのに、どこからともなく虫が飛んできて、ネズミやヘビ、亀まで集まってきます。
そして、名前すらなかった土地に人々の営みが始まる。やがて、風に乗って村人の祝歌が聞こえてくる。
…心底、水の偉大さを学ばされた50年でした。

こうした海外の途上国に比べると日本はとても豊かな国です。国土の2/3が森林に覆われ、雨もたくさん降る。日本の平野には先人が造り上げてきた用水路が縦横無尽に張り巡らされ、その水路の延長は約40万km(地球10周分)。
しかし、この豊かさはいつまで続くのでしょうか。
例えば水田。
我が社の創業時、日本の水田面積は約340万haでした。50年後は247万ha。農業人口の平均年齢は約70歳。跡継ぎもいない。
農業者のこれほどの高齢化は世界でも類がありません。
どんどん進んでゆく農業の国際化。
高齢化に経営不振が加わって大量の農家がリタイヤする時代を迎えています。
この国を二千年にわたって支えてきた水田社会の文化はいずれ消滅してしまう。

これまでの50年。そして、これからの50年。
三祐コンサルタンツの歩みは、日本の高度経済成長と重なっています。豊かさを経済だけで計ってきた時代だったとも言えます。
しかしと言うか、ゆえにと言うべきか、水、気象、自然、水田、先人などの恩恵を計る指標を日本の社会は持っていない。それらは、失ってみて初めてその壮大さに気づく財産です。
経済なくしても自然は存続するが、健全な自然なくして経済はありえない。
私たちはそんな単純な原理を、長い海外プロジェクトの経験で思い知らされました。
この先も、経済、あるいは科学技術はどんどん進化し続けるでしょう。
この先、人間に必要なのは百年、千年という座標軸ではないでしょうか。
これまでの50年。そして、これからの50年。
創業者の熱いロマンや信念は、50年を経た今も世界、国内、そして社内にも熱く流れ続けています。
千年少年 ― 私たち三祐コンサルタンツは、この先も同じ信念を持って歩み続けなければなりません。
世界中の村々から祝歌が聞こえてくる日まで。
そして、鳥の目に宿る哀しみが消え去る日まで。